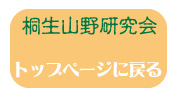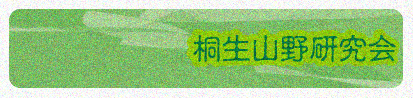
松浦武四郎が登った北海道の山
増田 宏
幕末の蝦夷地探検家松浦武四郎は登山家としても知られ、諸国の名山を踏破している。蝦夷地探検の際にもいくつかの山に挑み、登頂記を残している。私は北海道の山に通う中で松浦武四郎に関心を持っていたが、中村博男著「松浦武四郎と江戸の百名山」(平凡社新書)を読んで北海道における武四郎の登山に改めて興味を抱いた。蝦夷地探検記録として公刊された「東西蝦夷山川地理取調紀行」には羊蹄山、阿寒岳、石狩岳(現在の大雪山)などの登頂記が載っており、これまで事実とされてきた。近年になって武四郎の調査記録「東西蝦夷山川地理取調日誌」の存在が判り、この日誌から武四郎の研究家秋葉実氏により羊蹄山には登っていないことが明らかにされた。また、秋葉氏は阿寒岳登山も事実ではないと指摘している。
しかし、中村氏の前記著書では石狩岳登頂を事実としており、私は公刊本「東西蝦夷山川地理取調紀行」と調査記録「東西蝦夷山川地理取調日誌」を比較することにより武四郎の北海道における登山を検証してみた。その結果、羊蹄山と石狩岳登頂記は創作であるが、雌阿寒岳登頂は事実と分かった。また、道東の摩周岳、西別岳、日高山脈南部の観音岳登頂を確認した。
羊蹄山
公刊本「後方羊蹄(しりべし)日誌」では安政五(一八五八)年二月四日(新暦三月一八日)に羊蹄山に登っている。後方羊蹄日誌の登山記を要約すると以下のとおりである。
二月二日に雄岳(尻別岳)の下に達してそこに祠を置き、木幣を捧げてから雌岳(羊蹄山)の登攀にかかった。三日は二合目に泊まったが、寒さで巨樹が凍裂して地震のようで終夜眠れなかった。翌四日の未明に出発して四合目で日の出となった。風は刀のように顔面を打った。六合目で樹林帯を抜け、八合目からいよいよ険しくなり、午後ようやく頂上に達した。頂上は富士山のように窪んでいて周囲が一里半ばかりある。冬はその凹地に熊が冬眠しており、現地人は春を待って熊を獲るという。自分が登った時は帰りを急がされたので一頭も獲ることができなかった。
この記述から武四郎は積雪期の羊蹄山に登頂したと考えられていたが、後に存在が明らかになった調査日誌の行程からこの登頂記は真実でないことが判明した。安政五年の調査記録戊午東西蝦夷山川地理取調日誌第一巻「東部作発呂留宇知之誌」によると、武四郎は二月三日にウス会所に泊まり、四日にアブタへ向かっている。このことから羊蹄山登山は創作であることが判る。また、登山紀行の部分のみ漢文で書体が異なっており、頂上の凹地に冬眠している熊を時間がなくて獲れなかったなど荒唐無稽な記述からも事実でないことは明白である。武四郎は登山家として羊蹄山に興味を持ったが、おそらく冬期の登頂が困難で果たせなかったので伝聞から登頂記を創作したのだと思う。登路の描写や頂上の地形、熊の話などはアイヌの人からの聞き書きであろう。
 後方羊蹄日誌表紙 |
 羊蹄山(真狩から) |
石狩岳(大雪山)
公刊本「石狩日誌」では安政四(一八五七)年閏五月二日(新暦六月二三日)に石狩岳に登っている。なお、「石狩岳」は現在の石狩岳ではなく、大雪山のことである。石狩日誌の登山記を要約すると以下のとおりである。
一日は岩窟で泊まり、焚火をして横になったが、寒さで眠れなかった。翌二日に頂上に向かった。白銀のような積雪があり、滑るので危ない。一時(二時間)ほど経って半分ほど登ったように思ったが、四方一面の靄で何も見ることができなかった。しばらくすると靄が吹き払われて周囲の山が見えてきた。それからしばらく登って頂上に達した。周囲の山を眺望していると雲霧が押し寄せてきてよく見えなくなってしまった。寒風が肌を刺し、握り飯を食べようとしたら凍って白くなっていた。五葉松の枝を尻に敷き、杖を脇に抱えて頂上から滑り下って前夜の泊まり場に着いた。ここで米を煮て粥を食べてから道を急ぎ、川筋に泊まった。
安政四年の調査記録(丁巳日誌)第六巻「再篙石狩日誌」では五月一日に湧駒別・天人峡付近を調査しており、その中に登山の記載はなく、行程から石狩岳(大雪山)登山は事実でないことが判明した。湧駒別から初夏の大雪山に登るのは当時でもさほど困難でなかったと思われる。武四郎は登山家として大雪山に関心を持ったが、おそらく日程上登る暇がなかったのでアイヌの人からの伝聞を登頂記として記したのかもしれない。
雌阿寒岳
公刊本「久摺日誌」には安政五年三月二七日(新暦五月八日)の阿寒岳登頂記が記載されている。ここでも登頂記の部分のみ漢文になっている。この紀行では阿寒岳とあり、雄阿寒岳か雌阿寒岳か明確に記していない。深田久弥の日本百名山では雄阿寒岳だと推測しているが、記述と挿絵を比較検討すれば久摺日誌の阿寒岳は雌阿寒岳であることが判る。雌阿寒岳登山について、調査記録では同日に舟で阿寒湖巡りをしていることから秋葉実氏は事実でないと述べている。
しかし、戊午日誌第八巻「東部安加武留宇智之誌」に前日二六日のマチネシリ(雌阿寒岳)登頂の記載がある。久摺日誌の紀行とは内容が異なるが、この登頂記から雌阿寒岳登山は事実だと考えられる。以下に戊午日誌の登頂記抜粋を掲げる。
ルベシベ 是アカン越の頂上なり。是より我土人三、四人を召連、岳え上る。三尺に壱尺五六寸の五鬚松青毛氈を敷きしごとく一面にして、少しのすきもなく生たり。其うつくしさ譬ふるものなし。其松の下を見るや氷雪うず高く、未だ少しも不消。其よりいよいよ山は峻敷なるを、凡十丁も上るや、上はいよいよ風厳敷なりて、少しも足を留むべかりしなり。山もいよいよ巌多くなりて峻敷、其より凡二十余丁と思う頃雪路に成りて、足いたく凍る計なり。其雪路を七八丁上りてマチ子シリ頂上に至る。此処より東を見る哉、アカン沼を眼下に見、其を越てピン子シリ、其を男アカンと云。ピンは雄也、マチ子は雌也、合せて是を雌雄の山と云。扨是より雪路に尻を突て辷り下るに、土人等は凡十丁とも思う処を只一息に辷り下りぬが、我は如何にも恐ろしくて、左え転び、右え転等して、如何にも暇取りしが、漸々の事にて雪路を離れたり。しばしにてルベシベえ下る。
 久摺日誌挿絵 阿寒岳 |
 阿寒湖から雄阿寒岳 |
 雌阿寒岳 |
 雌阿寒岳山頂と阿寒富士 |
摩周岳(カムイヌプリ)・西別岳
「久摺日誌」の記述によれば、雌阿寒岳登頂後、武四郎は四月六日(新暦五月一八日)にカムイヌプリ(摩周岳)、翌七日に西別岳に登頂している。戊午日誌第十一巻「東部摩之宇誌」には四月六日のカモイ岳登頂が記され、戊午日誌第十二巻「東部奴宇之辺都誌」には四月七日のニシベツ岳(ニシベツノボリ)登頂が記されている。カモイ岳はカムイヌプリ、ニシベツ岳は西別岳であり、両山の登頂も事実であることが判る。公刊本の「久摺日誌」、調査記録の「戊午日誌」を比べると内容はほぼ同じであるが、公刊本の久摺日誌の方が簡潔明瞭で整った文章である。摩周岳の登路は火口壁の崖沿い、山頂は高度感のある岩場であり、登頂記と符合している。西別岳山頂を峨々たる岩と記載しているが、この山頂は現在の西別岳山頂(八〇〇㍍)ではなく、その東の七八七㍍峰と考えられる。以下に「戊午日誌」の抜粋を掲げる。
カモイ岳
一歩を過つ時は湖中に墜落する様に思はれ、如何にも恐きが故に、是より廻りて昇ること凡三丁、此処に至るや右はますます直立壁のごとく、左りもまた崩れ岩にて数十丈の谷に落るべき処なる也。よつて、此処昔より土人等通りしもの有か無かと問しかば、一人も昔より通りしもの無かれども、ニシハ跡より来るが故に、凡行ことかと思ふて我等も先立行也と云に大にあきれ、さて、そは致したり、其方共先え行まゝ行るかと我も思ひ来りしなりと云はヾ、誰も此処え来りしものなし云に大き驚き、然し是より来る故に先是非とも行て見べしとアヘウツヌカル云に、如何にも馬の背の如くなり。這ても其身ふるえたりけるが、辛うじて其頂に上りぬ。此頂上にて四方を眺望せんと思えども、目眩なして留りがたき故、また東の方え這下りぬ。ニシベツノボリ
ルベシベ 此処ニシベツ岳、マシウ岳の其間の少し低みなり。是より峯まゝニシベツ岳の方えと志さし行き、針位卯(東)に向ふに、左りポンケ子カイトコ、右ニシベツイトコの沢脈なり。小笹原にして処々樺木の屈曲たる有、また五鬚松の地につき這廻りたる有、また奇岩怪石の峨々としたる処々に突出す。其眺望筆紙の及ぶ処にあらず。しばし上りてニシベツノボリ頂上に至る。此辺峨々たる岩にして一ツの峯をなし、其間に五様(葉)松這二三間下に樺木の屈曲たるもの五六尺計なるが生たり。
 久摺日誌挿絵 カムイヌプリ |
 摩周岳(カムイヌプリ)遠望 |
 摩周岳(カムイヌプリ)山頂から摩周湖の展望 |
 西別岳 右側の頂が787㍍峰 |
観音岳
中村氏の著書には日高山脈南端の豊似岳登頂が記されている。戊午日誌巻外「東部登武智志」には安政五年七月二四日にトウフチノホリに登った詳細な記述がある。中村氏はトウフチノホリを豊似岳(一一〇五㍍)としているが、カモイトウという沼の近くにある峻嶺との記述及び挿絵から豊似湖の南西に聳える観音岳(九三二㍍)の誤りである。秋葉実氏編集の戊午日誌脚注でもトウフチノホリを観音岳としている。観音岳の旧名はトヨニヌプリでその名が現在の豊似岳に移ったらしい。この山は霊山で以前に登ろうとした人が途中で大雷雨にあって果たせなかったことを武四郎は聞いていたが、岳の神が夢に現われ、山に登って木幣を捧げ、下山したら御神酒を供えるよう告げたので、翌日アイヌの案内者二人を伴い登ったと記している。少し長いが、以下に「戊午日誌」の抜粋を引用する。
トウフチノホリはホロヰツミ領分にして、サルヽ番屋を出立し、弐里半にしてトウフチ峠有。是即トウフチ山のつゞきなるが故に此名有るなり。其峠の峯つゞきにして北面に当り、峨々たる一ツの峻嶺にして、其名義は此麓にカモイトウと云る周り凡一里計の深き沼有。よつて此名有りと。トウフチとは沼端と云儀也。古えよりして此嶺に上ることを禁じて有けるよしにして、曾て人を上げず。よつて余辰のとしも此念有て当山え上らん事を乞しに、案内の者の云るには『近年も此処え登り給ひし人有りしが、山の半腹まで到り給ふ哉、四方に黒雲まゐ下り大雷・大雹雨車軸を流して、一歩も前に得ずして帰り玉ひし』と申せしかば、如何にも其山容の毎ならざるもかく哉と、空敷過せしを遺恨と思ひ居たる処、今度こそと思ひ居たりしかば
七月二四日 サル番屋にて調役山村某、医師大内某等と同宿せしを、我独イソラム、エクレの両人を召連、駿足の馬をとらせ、是に乗りて五ツ(8時)前に此処(トウプチ)え着し、峠へ来るや我イソラムえ『此山に神霊有て、夕べ我が寝たる処え白髪の土人一ツの白衣を着し忽然と現し、夢の如く現の如く我に談ていえるには、我はトウフチ岳の神なり。性酒を好て有るも此頃一滴の酒をも我に供ふるものなし。貴人今日我が岳に上り一本の木幣を削りて立、それより下り玉ひて御神酒を我に手向呉といはるゝ哉と思ひしかば、夢はさめたり。依て今日は上りて木幣を一本建、其より下りて会所にて酒を買て上るべし』と申し『依て其方共案内を致す哉』と尋し処、案内のイソラムもエクレも神の教えと云、曾下りて御神酒を上ると云、それなら我を案内せんことを諾す。其よりして此処え荷物を置上るに
其山一面岩菅にして辷り、其下大岩簇々と有り、如何とも足留り無きが故に難渋仕候処、凡十七八丁にて四方よく見え、其風景いわんかたなし。また十丁も上るや只岩石のみ簇々として、其間樺の木多し。また弐三丁過て頂に上る哉、大岩畳み重りし処え五様(葉)松地を這て生、其処に蟻多く生したり。其蟻大きく足の如く羽有りて飛あるき、少しも腰を掛て休みがたし。足爪立にして四面の風景を図し、イソラムに木幣を作らせて納め、先以無難にして下りしに、実に蝦夷地開拓の一吉兆なるかや。九ツ(12時)過峠え下りしに、漸々山村、大内も来り居て、我が下るを待居られ、同道して七ツ(4時)過ホロイツミ会所え着し
結論
なお、中村氏の著書には安政三年四月の雷電山・椴(とど)山登山に触れているが、安政三年の調査日誌「竹四郎廻浦日記」を見る機会がなかったので両山については確認していない。
以上から松浦武四郎の紀行にある登山記のうち羊蹄山と石狩岳(現在の大雪山)の記述は事実でなく、創作であることが判明した。いずれの登山記もアイヌの人からの聞き取りを元に書かれたと思われる。東西蝦夷山川地理取調日誌(丁巳日誌二巻、戊午日誌三巻)の解説で公刊本が調査日誌に興を添え、聞き書きを付け加えたものであると武四郎自らが記している旨秋葉氏は書いている。
しかし、雌阿寒岳、摩周岳(カムイヌプリ)、西別岳、観音岳の登頂は事実であることが裏付けられた。私は武四郎の主要な登山について刊行本と調査日誌を読み比べただけであり、日誌を詳細に読めば北海道における武四郎の登山について新たな事実を解明できるかもしれない。
なお、武四郎の文章は左記参考文献の「丁巳日誌」「戊午日誌」から引用した。引用文中の「土人」は土着の住人であるアイヌの人々を指す。武四郎はアイヌ民族と対等に接し、そのふれあいを『近世蝦夷人物誌』として著している。
参考文献
丁巳東西蝦夷山川地理取調日誌 上下(秋葉実編 北海道出版企画センター刊)
戊午東西蝦夷山川地理取調日誌 上中下(秋葉実編 北海道出版企画センター刊)
松浦武四郎紀行集 上中下(吉田武三編 冨山房)
松浦武四郎と江戸の百名山(中村博男著 平凡社新書)
(山の本2008年冬号掲載)