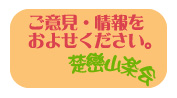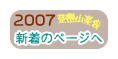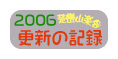いつ頃から山に登るようになったかは覚えているのですが、なぜ山に登るようになったかは判然としません。高校入試が終わった頃、中学校の同級生達と鳴神山から吾妻山までの縦走をしたことがありました。今思えば無謀なことだったかも知れません。5〜6人で登って、水筒を持っていたのが2人、後は缶ジュースを持っていればいい方で、弁当も雨具も持たずに高沢入口でバスを降りて、鳴神山に登ってしまいました。吾妻山まで行くことが最初から決まっていたのかどうか、鳴神山に登るのさえ、皆が集まってから決まったのだと思います。中学生から高校生の男子はとにかく体力だけはありますから、馬力だけで、あっさりと鳴神山に登れてしまったように思います。まだカメラが高価な頃で、誰も写真機は持っていなかったように思います。想い出だけで写真は残っていませんので。
いつ頃から山に登るようになったかは覚えているのですが、なぜ山に登るようになったかは判然としません。高校入試が終わった頃、中学校の同級生達と鳴神山から吾妻山までの縦走をしたことがありました。今思えば無謀なことだったかも知れません。5〜6人で登って、水筒を持っていたのが2人、後は缶ジュースを持っていればいい方で、弁当も雨具も持たずに高沢入口でバスを降りて、鳴神山に登ってしまいました。吾妻山まで行くことが最初から決まっていたのかどうか、鳴神山に登るのさえ、皆が集まってから決まったのだと思います。中学生から高校生の男子はとにかく体力だけはありますから、馬力だけで、あっさりと鳴神山に登れてしまったように思います。まだカメラが高価な頃で、誰も写真機は持っていなかったように思います。想い出だけで写真は残っていませんので。
多分、あっさり登ってしまったので、誰ともなく吾妻山に行こうといいだして、向ったように思います。途中で水分は全てなくなり、3月末だったので、多少残っていた雪でのどを潤し、それでも元気に歩いていた記憶があります。吾妻山が近づくにつれ、雪もなくなり、喉の渇きが耐えきれなくなりましたが、当時は運動中に水分をとることはいけないことだと教えられていたので、我慢できたように思います。吾妻山からは水道山に当時あった売店をめざし、走るように下りました。まずたらふく水を飲み、売店でアンパンやらジャムパンを買って、腹を満たし、また水を浴びるように飲んだ記憶があります。
それからしばらく山とは縁のない生活が続きました。山国に住んでいますから、主体的には登らなかったということで、山に連れていかれたことはありましたが。
二十歳頃から、何となく週末には山に登るようになり、時には友人を誘って主に北アルプスや谷川を歩くようになりました。登山がブームだった頃で、新宿発の夜行列車、上野発の夜行列車に乗るために何時間も前から列が出来ていました。
社会人になってからは、一人で登ることが多くなり、南アルプスや奥秩父に足がむき出しました。雁坂峠や仙丈岳、塩見岳は、今でも好きな山の一つです。
で、楚巒山楽会の初代会長に会い、今の山歩きの原典ともバイブルともいうべきスタイルの洗礼を受けました。山道を20分も歩くと、やおらザックからコンロを取り出し、ポンピングをして白ガスに火をつけます。お湯を湧かし、本格的なドリップコーヒーを入れます。景色のいい所では何本も煙草をふかします。パイプ煙草に火をつけることもあります。山の中でゆったりとした時間を過します。テント場では大宴会。山頂まで行っても、行かなくても、十分に山の楽しさが味わえます。そうか、ただ頂上に向うだけが山登りではなかったんだ。10分でも20分でも何時間でもぼーっとしてていいんだ。
で、浅海八幡山でした。ここは、例の部類に入るのですが、これを山と呼ぶのは流石の私も忸怩たるものがあり、紹介するのを躊躇っていました。しかしながら、藤井さんの桐生の地質で、ここは赤城の流れ山という記述があり、群馬で一番低い山といわれる伊勢崎の八寸権現山と同じだということなので、晴れて紹介してしまいました。概念図と写真をみていただければ、お分かりになると思いますので、と、いうことです。
南アルプス北岳山頂 最前列が代表幹事 後は会員の方々


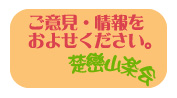

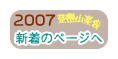
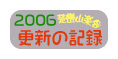

 いつ頃から山に登るようになったかは覚えているのですが、なぜ山に登るようになったかは判然としません。高校入試が終わった頃、中学校の同級生達と鳴神山から吾妻山までの縦走をしたことがありました。今思えば無謀なことだったかも知れません。5〜6人で登って、水筒を持っていたのが2人、後は缶ジュースを持っていればいい方で、弁当も雨具も持たずに高沢入口でバスを降りて、鳴神山に登ってしまいました。吾妻山まで行くことが最初から決まっていたのかどうか、鳴神山に登るのさえ、皆が集まってから決まったのだと思います。中学生から高校生の男子はとにかく体力だけはありますから、馬力だけで、あっさりと鳴神山に登れてしまったように思います。まだカメラが高価な頃で、誰も写真機は持っていなかったように思います。想い出だけで写真は残っていませんので。
いつ頃から山に登るようになったかは覚えているのですが、なぜ山に登るようになったかは判然としません。高校入試が終わった頃、中学校の同級生達と鳴神山から吾妻山までの縦走をしたことがありました。今思えば無謀なことだったかも知れません。5〜6人で登って、水筒を持っていたのが2人、後は缶ジュースを持っていればいい方で、弁当も雨具も持たずに高沢入口でバスを降りて、鳴神山に登ってしまいました。吾妻山まで行くことが最初から決まっていたのかどうか、鳴神山に登るのさえ、皆が集まってから決まったのだと思います。中学生から高校生の男子はとにかく体力だけはありますから、馬力だけで、あっさりと鳴神山に登れてしまったように思います。まだカメラが高価な頃で、誰も写真機は持っていなかったように思います。想い出だけで写真は残っていませんので。