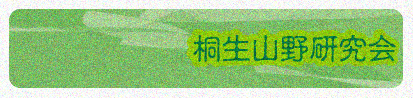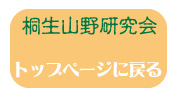カッコソウは、なぜキソコザクラか?
桐生山野研究会 REI KESAMARU
五月になると、必ず出かける山がある。鳴神山である。ニリンソウの咲き乱れる沢筋をたどり、ほんの少しの薮をかきわければ、そこはカッコソウの自生地である。近年では、個体の数に減少傾向が見られるが、やわらかい陽射しを受けてひそやかに咲いているこの花を見ると、季節の訪れをしみじみ感じる。
この、野草とはとても思えないほど美しいカッコソウは、別名キソコザクラとも呼ばれるサクラソウ科の多年生草本である。楕円形の葉に白毛を有し、四〜五月頃に花茎を伸ばし、やや薄い紅紫色の花をつける。自生地としては鳴神山とその周辺のみであり、全国的に見ても大変貴重な植物である(四国にはシコクカッコソウと呼ばれる変種があるが、実際に確認してみると、カッコソウに比べ概して多毛な個体が多く、また、どちらかというと、カッコソウのほうが草姿に野趣を強く感じるなどの相違点があり、本稿では特に取り上げない)。
さて、先ほどの別名であるが、なぜキソコザクラと呼ばれるのであろうか?カッコソウはその学名をP(プリムラ)・キソアナ・ミケルという。また、牧野富太郎がP・キソアナのことを『草木図説』のカッコソウとは異なり、キソザクラだとした時期もあって、キソコザクラという別名が定着していったものと思われる(ミケルとはオランダ人で、カッコソウの学名を発表した植物学者)。
ここでひとつの疑問が生じる。なぜ「キソ」なのか?「キソ」は木曾である。ミケルは木曾で採集されたカッコソウに、P・キソアナと名付けたのである。カッコソウが木曾にもあった?ひとつの疑問から謎が次々に生じてくる。本当に木曾にカッコソウの自生があったのだろうか?
じつは、現在はもちろん、過去にあっても木曾にカッコソウの自生があった証拠は何一つないのである。現在、日本全国いたる所で専門家やアマチュアの植物愛好家の調査、探訪が行なわれているが、未だにカッコソウ発見の報告はどこからも聞かれない。専門家の間でも、木曾におけるカッコソウの存在については疑問視されるむきが強い。
そして、カッコソウを木曾で採集したのは誰か?どのような経緯からはるばると海を越え、ミケルの手元にまで渡ったのであろうか?こうなってくるとまるでミステリーであり、私の手に負える問題ではなくなってくる。手元にある資料はとても乏しいのだが、日光や足尾の山、そしてそこに咲く花々を愛する人間の一人として、簡単に推理をしてみたい(ただし、これはあくまで歴史や植物学的に考察を加えた結果ではなく、きわめて底の浅い知識しか持ちあわせていない人間の書いたフィクションと思っていただいた方が間違いないであろう)。
1823年、シーボルトが長崎出島の医官として初来日した。そして1829年にシーボルト事件(スパイ容疑)で国外追放になるまでの間、及び、再来日した1859年のさい、彼は彼自身の採集品や、尾張の本草学者伊東圭介らから提供を受けたものを本国オランダに送った。この中に、くだんのカッコソウが含まれていたことはもちろんであり、それによってオランダの植物学者ミケルがP・キソアナ・ミケルと命名したのである。
繰り返していうが、キソアナと命名したのはミケルであるが、ミケルが勝手に「採集地・木曾の高所」としてしまったわけではないのである。このことは重大である。つまり、ミケルの手に渡る前の段階から、すでに「採集地・木曾の高所」となっていたのである。
先に述べた理由により、木曾にカッソソウの自生がなかったとすると、
(1)「採集地・木曾」の、本当の自生地はどこであったのか?
(2)ミケルが命名し、現在ライデン博物館に保存されているカッコソウは、一体誰が採集したものなのか?
(3)なぜ、「採集地・木曾」となってしまったのか?
という三つの疑問点が整理されてくることになろう。
このあたり、学者間でも論議の的となっているようで、ずいぶん以前の新聞に大きく取り扱われていたことは覚えているのだが、スクラップしておかなかった迂闊さを今ここで後悔してもはじまらない。識者の冷笑を覚悟で私の考えを述べてみよう。
まず、(1)の件に関して。これは、やはり木曾ではなかったものと思われる。前述したように、現在に至っても木曾にカッコソウの自生は全く知られていないのだ。植物学史上今日ほど、カッコソウのみならず各種植物に関して調査、研究の進んでいる時代はないのである(もちろんアマチュアのレベルも高く、それがサクラソウ科の植物であれば、カッコソウであるか、又は、類似する同じ科の草本であるオオサクラソウや、単なるサクラソウであるかを見分けるくらいのことは、そう難しいことではないのである)。
本稿執筆にあたって、各種植物関係の文献を調べても見た。植物図鑑の中には、カッコソウの自生地として、北関東(つまり鳴神山系)及び、中部地方南部(つまり木曾)と記してあるものが多い。しかし、ここで声を大にして言いたい。執筆者の誰か一人でも、本当に木曾に於けるカッコソウの自生地を見たことがあるのだろうか?「ライデン博物館に保存されているカッコソウの自生地が木曾となっているから、かつては自生があったのかもしれない」と、控え目な(好ましい)表現をしたものが見当たらないのが不思議である。
思うに、この植物標本のあるがゆえに、今日に至るまで、学会の植物分布図には木曾のカッコソウが(所在不明のまま)掲載されるようになってしまったものと思われる。たった一本だけが木曾(?)で発見され、異境の地で泣いているカッコソウは、思うだに哀れである。このカッコソウのために私はあえて言いたい。「ライデンのカッコソウの故郷は、群馬県の鳴神山系だったのだ」と。
(2)に関して。このカッコソウを採集した人物の名は、手元の資料によれば、尾張の本草学者伊東圭介ということになっている。シ−ボルトにカッコソウを渡したのもこの人物であるようだ。後者については、ほぼ正しいようである。しかし、前者については疑ってかからねばならない。
本当に伊東圭介が採集したのなら、尾張から当地までの長旅がなければならない。当然そこには「伊東圭介旅日記」に類するものが残されてしかるべきであろう。調べ、分類し、記録するのが本業の学者であってみれば、筆を執るのに苦労はなかろう。その圭介にして、カッコソウの採集話がなにも残されていないということや、当時の交通事情などを考えあわせてみると、伊東圭介は鳴神山系には来なかったと考えざるを得ない。つまり、カッコソウの採集者は伊東圭介ではなかった!では、カッコソウは、一体誰が採集したのであろうか?伊東圭介はシ−ボルトに師事したのち、いわば一派をなした人物である。当然そこには複数の弟子や協力者がいたはずで、有用な、あるいは珍しい植物を求めて、各地に散っていたのではないだろうか。その中の誰かが、鳴神山系でカッコソウを採集したとは考えられないだろうか。珍しい花に、圭介は気もそぞろとなり、『シ−ボルト先生も、さぞ喜んでくださるだろう』と、思ったか思わなかったか…。
じつは、ここまで書いた段階で、以前に花の会で知りあったT先生に電話をかけさせていただいた。このあたりの事情について教えを受けたいと思ったからである。その結果、協力者があった点までは一致していたが、さすがにT先生である。協力者と思われる人物の具体的な名をあげて、さらに追及を続けているとのことであった。その話をここに掲載することができたなら、駄文も重みをますというものだが、もちろんそんな失礼なことはできようはずがない。しかし、渡辺華山の妻や、伊東圭介の弟子で伊勢崎の本草学者の名が話に出てきたことだけは、書き記させていただきたいと思う。
結局、(2)の結論として、伊東圭介は採集していなかった。採集したのは彼の弟子、あるいはなんらかの形での協力者ということになるだろう。
ようやくたどりついた(3)は、完全に空想の世界である。どんな資料を調べても「鳴神山系で採集されたカッコソウが、どうして木曾と誤記されたか?」などと書かれたものは一つもない。あろうはずがないのである。例のカッコソウは木曾の産として処理されているのだから…。
もっとも、いっそのこと木曾に本当に自生地があってくれたら…、これですべてが解決となる。悩むことなど何もなくなるのだ。カッコソウは、日本全国で自生しているのはここだけ…と、誇らしく思っていられなくなるのは少々さびしいが…。
幸か不幸か、カッコソウの自生地は目下のところ当地だけなので、空想の世界を自由に楽しめるというものだ。思いつくままに書き連ねてみよう。
(a)カッコソウは、案外に古くから知られていたようである。いずこの世界、いずこの時代にも好事家というものはいるものだか ら、鳴神のカッコソウが、木曾のどこかで栽培されてはいなかったろうか。それを持ち帰った人間によって「産地・木曾」となっ た。
(b)圭介のもとに、鳴神山系のカッコソウを持ち帰ったものがいた。
「先生、これはカッコソウという珍らしい花です」
「おお、これは美しい花だ。いったいどこで採集したのか?」
「はい、木曾路を経まして…、それは難儀な旅でございました」
「ふむ。木曾か…」
(c)初めのうちは「産地・キリウ」となっていたが、人手を経るうちに「産地・キソ」となってしまった。
(d)鳴神山周辺で、「キソ」と呼ぶ地名はないか?
(e)標本をたくさん扱っていたので、産地不明となったものを適当に「木曾」としてしまった。これは、シ−ボルトにも伊東圭介 にもいえることである。
(f)シーボルトは、日本で採集した植物標本に、ラテン語で学名を記載した。しかし、異国のことであるから不明な植物も当然ある わけで、そのようなものには暫定処置として日本における種名をアルファベットで発音どおりに記載した。このような標本が本国 オランダに送られて、日本語に不馴れな助手にでも整理されたとしたらどうだろう。ほかに「採集地・木曾」なる標本がたくさん あって、「採集地・桐生」なる標本がたった一つであったとしたら…。いろいろな空想を楽しんだ筆者は、そろそろ疲れた。最後に識者の結論を紹介しよう。
「単なる誤記でしょうね、あれは…」
桐生山野研究会発行「回峯」第2号 1988年より